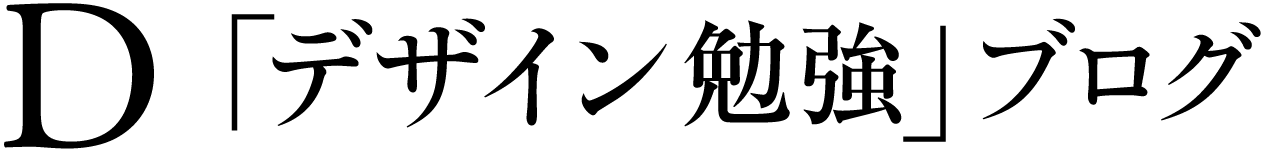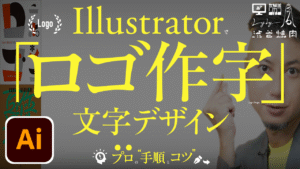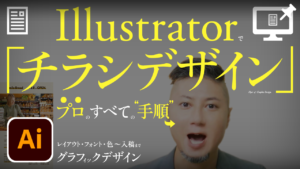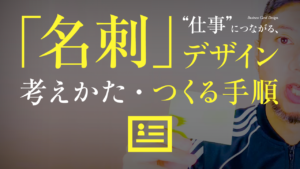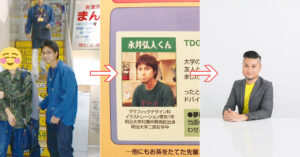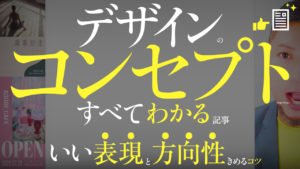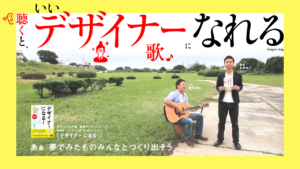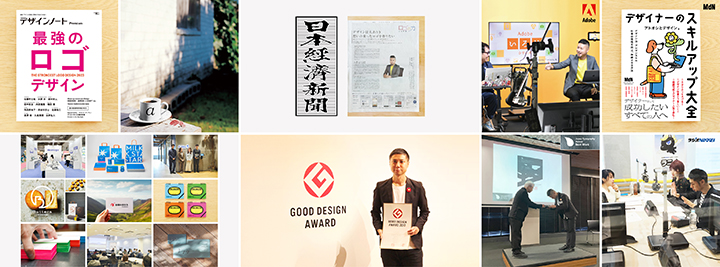
この記事で、習得できること
「ロゴデザイン」には、様々な表現方法があります。その中でも「作字ロゴ」は、「文字の形」において、独自性と表現力の大きな魅力があります。
この記事を読むと、「作字ロゴ」の意味、「優れた作字ロゴ」を作る方法、「Adobe Illustrator(イラレ)を使った、実践的な制作テクニック」を習得できます。
デザイナーやクリエイターとして活動している方はもちろん。自分のブランドやプロジェクトのために、“独自ロゴをデザインしたい”方にも参考になる記事です。
それでは、「作字ロゴ」のプロの考え方、実際の制作手順、完成までのプロセスを紹介します。
▲ この動画を見ると、より深く、「Illustratorでロゴ作字のデザイン。プロの手順とコツ」を習得できます◎
そもそも、「作字ロゴ」とは
「作字」の定義
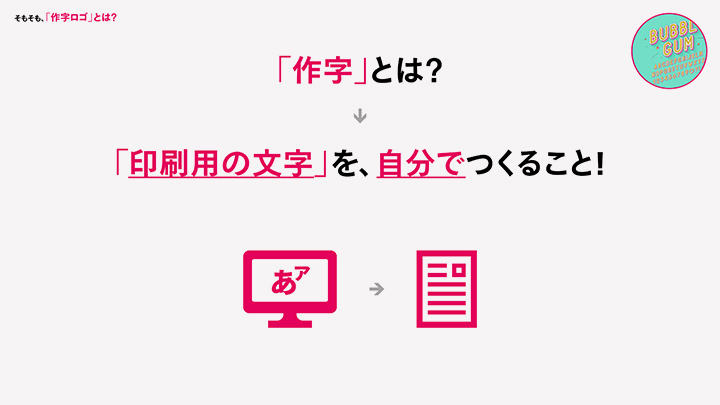
「作字」とは、広義には「“印刷用の文字”を自分で作ること」を指します。
ですので、“既存フォント”をそのまま使用するのは、「作字」とは言えません。
しかし、フォントを削ったり伸ばしたりして加工すれば、それは「作字」と呼べるでしょう。
「ロゴ」と「作字ロゴ」の違い
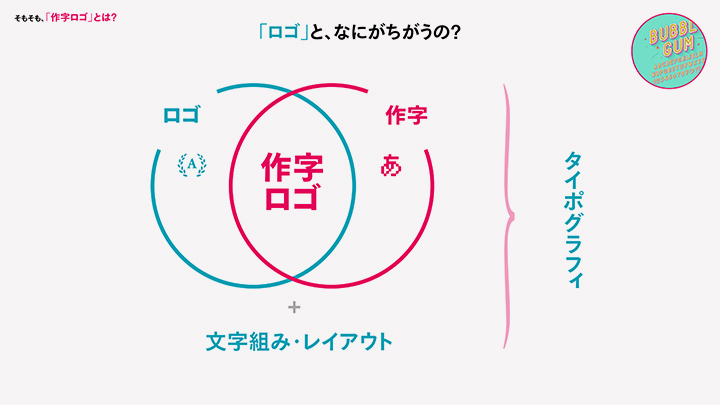
「ロゴ」と「作字」と「作字ロゴ」の間には、“明確な境界線”を引くことは難しく、「意味」や「目的」が重なり合う部分があります。
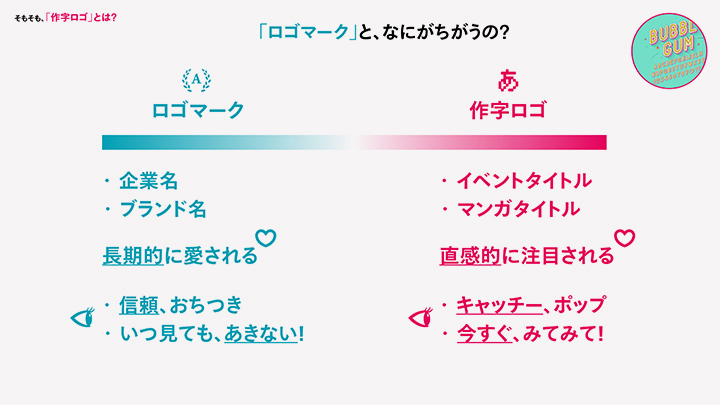
「ロゴマーク」は、“企業ロゴ”や“ブランドロゴ”を表し、「長期的に愛される」視点が強い傾向があります。“信頼性”や“落ち着き”といった要素を重視し、長年での使用を前提とした表現が多く見られます。
一方、「作字ロゴ」は文字形状に特徴があり、“イベントタイトル”や“漫画タイトル”など、「即時に注目を集めたい」シーンに使われます。キャッチーでポップな形が特徴で、「今すぐ見て!」と呼びかける効果を狙う傾向があります。
ただし、これらに“厳密な区分”はありません。
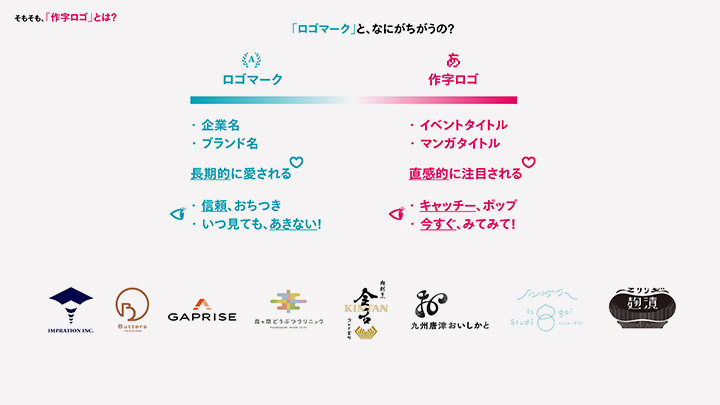
「ロゴマーク」でも即時的に注目を集めるデザインもあれば、「作字ロゴ」でも長年愛されるデザインもあります。
ですので、これらは、“緩やかな分類”として捉えましょう。
「タイポグラフィ」との関係
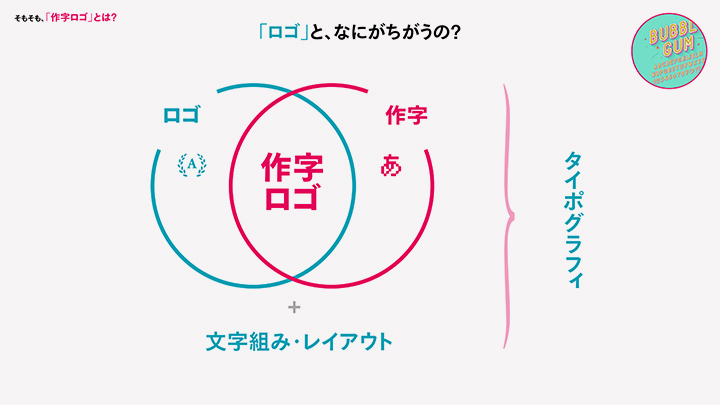
「タイポグラフィ」という言葉も、よく耳にしますよね。
「タイポグラフィ」は、「ロゴ」や「文字組み」や「レイアウト」、「既存フォントの使い方」など、「文字を使用したデザイン」という、“より広い概念・考え方”です。
「作字」や「ロゴ」を作る技術は、「タイポグラフィの一部」と言えます。
しかし、必ずしも、「“作字ロゴ”の技術がある = “すべてのタイポグラフィ”の技術がある」ということではありません。
バランスの良い「タイポグラフィの技術」をつけながら、「作字ロゴの力」をつけることをオススメします。
「良い作字ロゴ」の共通点
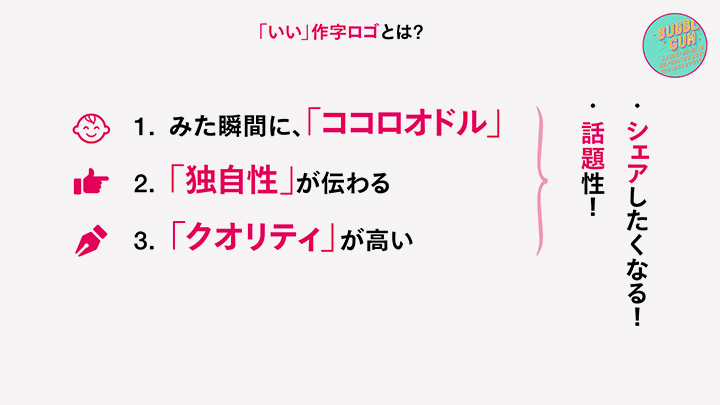
「良い作字ロゴ」には、「3つの共通点」があります。
- 見た瞬間に「心が踊る」
“視覚的なインパクト”があり、「見る人の心を動かす」デザインであること。 - 「独自性」が伝わる
「コンセプト」を感じられる、“特徴的な形状”を持っていること。他の作字ロゴでは表現できない、「独自の世界観」を持っていることが重要です。 - 「クオリティ」が高い
“揃えるべき部分”がきちんと揃えられているか、“同じ角度”で曲がっているかなど。「細部のクオリティ」が高いこと。
この共通点が重なる「良い作字ロゴ」は、話題性を生み、シェアされやすい傾向があります。
「良い作字ロゴ」は、形そのものの魅力だけでなく、その形に込められた、「意味」や「考え方」も含めて評価されます。
見た人に、「この作字ロゴには、こんな“意味”や“背景”があるんだ!」と知ってもらえると、そのデザインに対する理解がより深まり、魅力が増すのです。
作字ロゴを作る、「4つの手法」
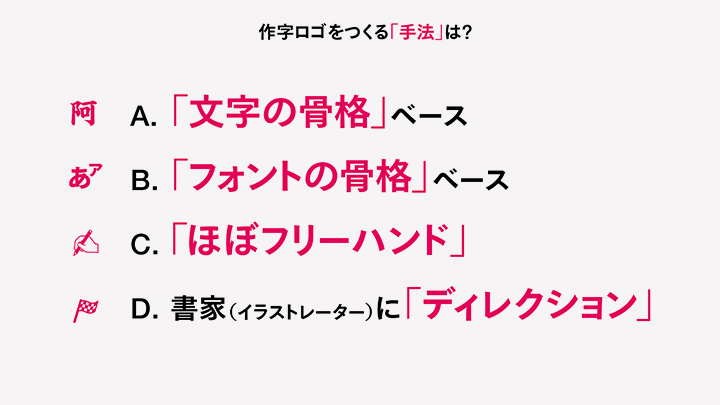
「作字ロゴ」を作るには、主に「4つの手法」があります。
- A. 「文字の骨格」ベース
- B. 「フォントの骨格」ベース
- C. 「ほぼフリーハンド」
- D. 書家(イラストレーター)に「ディレクション」
1つずつ、詳細を説明します。
A. 「文字の骨格」ベース
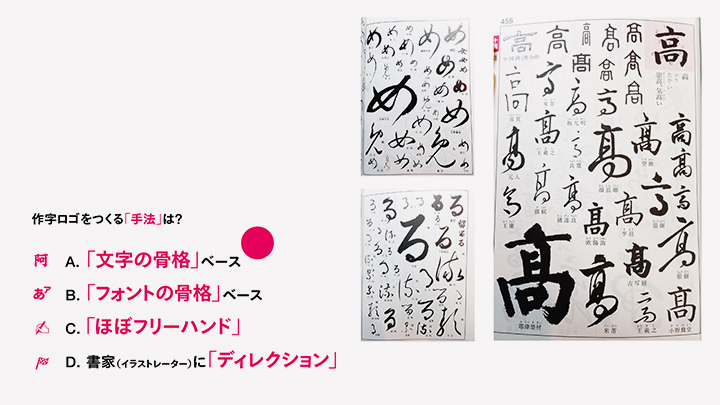
“漢字・ひらがな・カタカナ”などの「基本的な骨格」を参考にしながら、「オリジナリティを加えていく」方法です。
例えば。『高い』という“漢字”を「作字ロゴ」にする場合。“漢字”の歴史的な成り立ちや楷書、草書などの違いを理解した上で、どこに「オリジナリティ」を加えるかを考えます。
“ひらがな”や“カタカナ”にも、「筆や書き順の流れ」があります。
まずは、「ここで筆が勢いよく流れる」「ここに墨だまりができる」「ここで筆をしっかり止める」など、基本構造を調べて知る。
その上で、“それに従うか/あえて崩すか”を選択することで、「読みやすさ〜独自性」のパワーバランス・検証を行うのです。
◎ 「文字の骨格」の参考本
・「書体字典 漢字」野ばら社
・「書体字典 かな」野ばら社
B. 「フォントの骨格」ベース

「既存のフォント」を基本として、それを削ったり伸ばしたりして、「独自の要素を加える」方法です。
例えば。「丸ゴシック系のフォント」を基にして、“一部を削る”ことで、“軽さや抜け感”を表現するといった手法があります。
C. 「ほぼフリーハンド」

“文字の基本骨格”や“フォントの形状”をあまり参考にせず、「直感的に表現したい印象」や「独自性を重視」して、「フリーハンドで描く」方法です。
やや“アーティスト的な感覚”に近いかもしれません。この手法でクオリティを保つためには、Illustratorなどのツールで、“デザイン細部を調整する”作業が必要です。
D. 書家(イラストレーター)に「ディレクション」
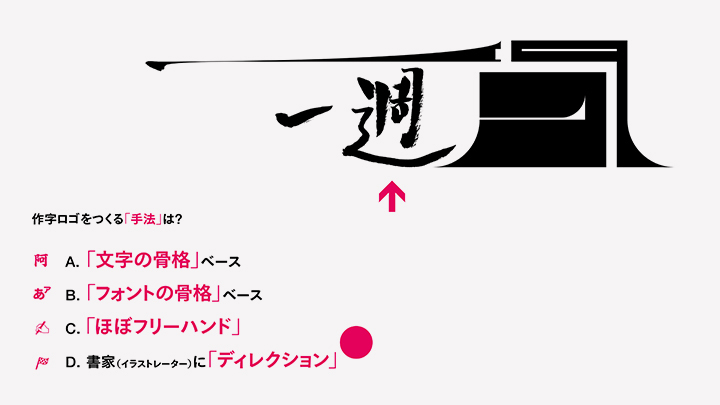
「書家」や「イラストレーター」に特定の文字を書いてもらい、それを「デザイナーが調整」して、作字ロゴに仕上げる方法です。
例えば。
01. デザイナー側から、「『荒々しい文字』という方向性・『参考の書(文字)』」というディレクションを、書家に出します。
02. そのディレクションをもとに、書家に「作字ロゴ用の『文字』」を書いてもらいます。
03. その「作字ロゴ用の『文字』」をもとに、デザイナーが、「Illustratorのパスに変換」して、Illustrator上にて細部調整を行い、作字を完成させます。
「コンセプト」と「印象」のレベル検証
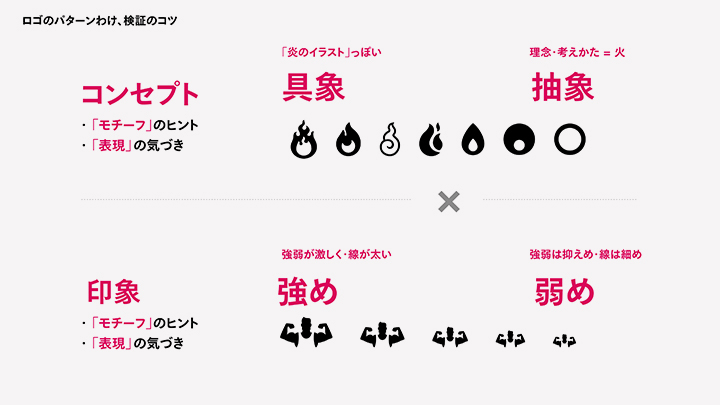
「作字ロゴ」の制作では、“どの手法を選ぶ”かと同時に、「コンセプト」と「印象」のパワーバランスの検証を行うことが重要です。
「コンセプト」:具象的〜抽象的
例えば。デザインコンセプトを「炎」として、「炎」をモチーフにした、ロゴをつくる場合。
誰が見ても、「炎」とわかる、「具象的な表現」にするか。
一見しただけでは「炎」と気づかないが、「抽象的な表現」にて、「炎の要素(“円形の輪を、炎として捉える”など)」を取り入れるか、を考えます。
「印象」:強め〜弱め
ロゴを見た人に、「どんな印象」を与えたいのか、を考えます。
例えば。「より力強さ」を感じさせたいのか、「やや落ち着いた」雰囲気を感じさせたいのか、など。
つくるロゴの表現によって、「与えたい印象」を明確にしましょう。
「コンセプト」と「印象」を掛け合わせる
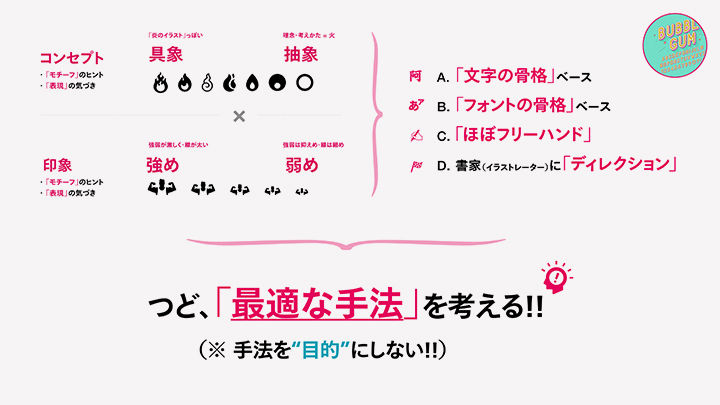
これらの「『コンセプト』:具象的〜抽象的」と「『印象』:強め〜弱め」を掛け合わせることで、「ロゴの表現の幅」が広がります。
ですので、「コンセプト」と「印象」を明確にした上で、“最適な手法”を選ぶことが大切です。
「この文字を、あの人に書いてもらいたい!」というように、“手法が目的”になってしまうことは避けましょう。
まずは、「コンセプト」と「印象」を考えてから、「“その表現”に合う、“最適な手法”を選ぶ」という順序をオススメします。
Illustratorで作字ロゴ、「つくる手順」
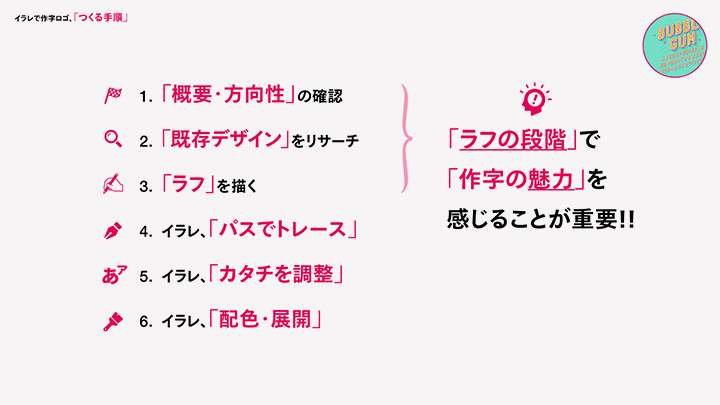
Illustratorを使った作字ロゴの「制作手順」は、下記の「6つのステップ」に分けられます。
◎ A.「Illustratorを使う前」の段階
・手順01:「概要・方向性」の確認
・手順02:「既存デザイン」のリサーチ
・手順03:「ラフ」を描く
◎ B.「Illustratorを使う」内容
・手順03:Illustrator、「パスでトレース」
・手順04:Illustrator、「カタチを調整」
・手順05:Illustrator、「配色・展開」
A.「Illustratorを使う前」の段階
・手順01:「概要・方向性」の確認
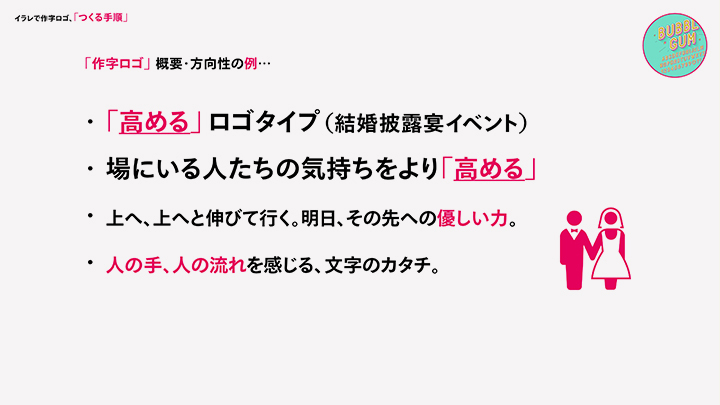
例として。「高める」という文字を、作字ロゴとして起こす場合。まず、「概要・方向性」を整理して、以下のように書き出します。
・つくる作字:「高める」
・概要:「結婚披露宴イベント用」のタイトルロゴ
・目的:場にいる人たちの気持ちをより「高める」
・印象:上へ、上へと伸びて行く。明日、その先への「優しい力」。
・表現の特徴:「人の手、人の流れ」を感じる、文字のカタチ。
・手順02:「既存デザイン」のリサーチ

つぎに。「日本語ロゴ」や「作字に関する書籍」などを参考に、様々な文字の形をリサーチしましょう。
あなたがつくる作字ロゴの「コンセプト」に合う「表現方法」を見つけます。そして、「なぜ、そう感じるのか?」を「言語化」して、「表現の特徴」をメモしておくと良いでしょう。
例えば。「(リサーチしている)既存の作字ロゴの『尖った部分』や『跳ねている表現』が、『上へと伸びていく雰囲気』に合っている」。「作字内に『心地よい抜け感』があると、『明るさ』や『日差し』を感じさせる」。などです。
◎ 「ロゴ作字」の参考本
・「ニホンゴロゴ 2」パイ インターナショナル
・「作字百景 ニュー日本もじデザイン」グラフィック社
・手順03:「ラフ」を描く
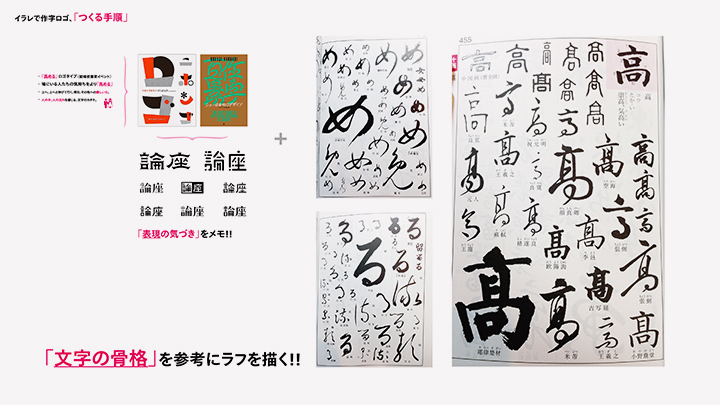
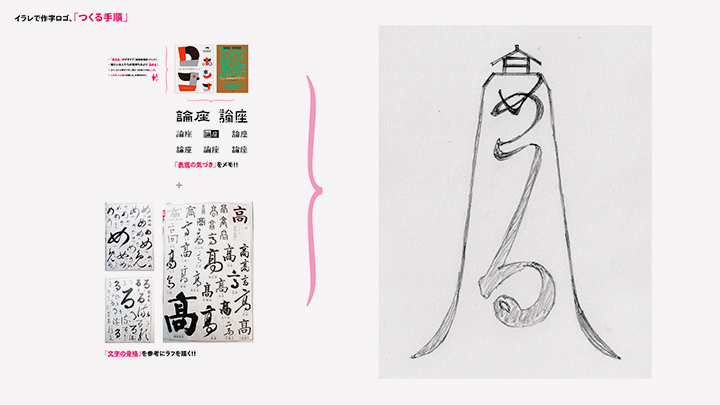
つぎに。リサーチで得た「表現のメモ」を参考に、「選んだ手法(例:文字の骨格ベース)」に基づいてラフを描きます。
例えば。「高める」という、作字ロゴの「ラフ描き」の場合。
「漢字の成り立ち」を調べ、「文字の骨格」を参考にした上で、下から上に見上げるような形で、「上へ上へと伸びていく」印象を描きます。
このような“リサーチ・参考視点”をもとに、複数のバリエーションを描き、比較した上で、「最もコンセプトに合うラフ案」を選びましょう。
・重要なポイント
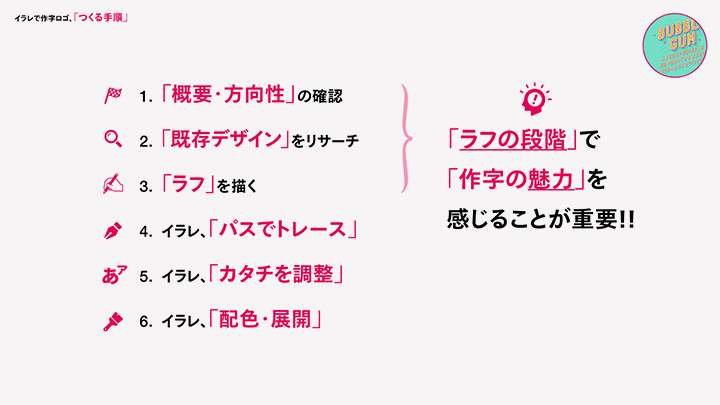
「作字ロゴ」の場合。「ラフ描き」の段階で「魅力を感じる」状態になっていない案は、Illustratorの作業に進まない方が良いでしょう。
「ラフ描き」の段階で、「独自性・オリジナリティ」があり、「伝えたい印象」を感じられる案ができてから、Illustratorでの作業に進むようにしましょう。
B.「Illustratorを使う」内容
ここからは実際に、「Illustratorを使った作字ロゴ」の制作手順を、具体的な事例を通じて解説します。
事例01:「獣喫茶 リカコ」
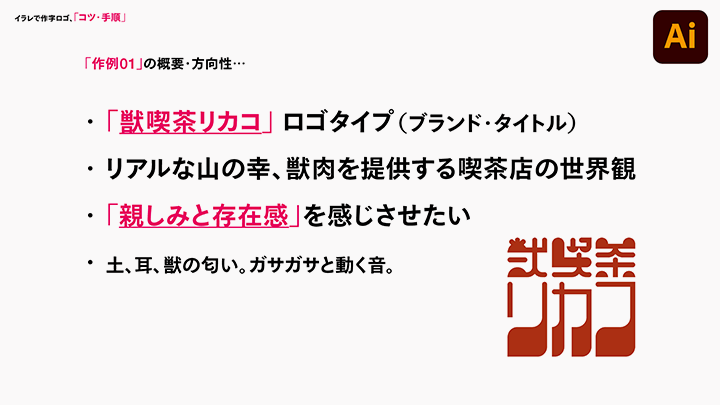
獣肉を提供する喫茶店、「獣喫茶 リカコ」の作字ロゴ。力強さと存在感、獣の雰囲気を感じさせるデザインです。
この「事例01」は、より丁寧に、“Illustratorでの制作手順・ポイント”を紹介します。
また、「事例01:獣喫茶 リカコ」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。
「獣喫茶 リカコ」、Illustratorでの“制作手順・ポイント”
- ラフ画像の配置
- Illustratorを立ち上げ、「新規ドキュメント」を作成
- 「ファイル」→「配置」にて、ラフ画像を配置
- 「整列パレット」にて、ラフ画像をアートボード中央に配置
- 「ラフ画像の透明度:30%」にして、トレースしやすくする
- ラフのトレース
- 新規レイヤーを作成し、「トレース」と名付ける
- 「四角形ツール」にて、基本的な形状を作成
- 「変形パレット」にて、調整しやすい数値に設定
- 「環境設定」にて「キー入力:0.05mm」にして、こまかな調整ができるようにする
- 「スマートガイド」をオンにして、図形同士を正確に合わせる
- 「Command+Y」にてアウトライン表示に切り替えて、形状を確認
- 図形の調整
- 「整列パレット」を使って、図形を正確に配置
- 「楕円形ツール」にて、円を作成する
- 「ダイレクト選択ツール」にて、パスの一部を削除して半円にする
- 「ペンツール」にて「パスの点」を追加して、形状を調整
- 「アンカーポイントツール」にて、曲線をなめらかに調整
- 「平均」機能にて、「パスの点」を整列させる
- 図形のコピペ・統合
- 同じ形状はコピー&ペーストし、反転させて、「対称形」を作る
- 「パスファインダー」で図形を統合し、一つのオブジェクトにする
- “統合前のオブジェクト”は、アートボード外に保存しておく
- 図形の微調整
- 「ガイドライン」を引いて、文字のバランスを整える
- 「揃えるべき部分」を、丁寧に揃える
- 色の検証
- 「コンセプト」に合わせて、茶色系の色を選択
- 「スウォッチ」から基本色を選び、細かく調整
- 印刷して、紙で確認
- 「CMYKの数値」を微調整して、最適な色を決定
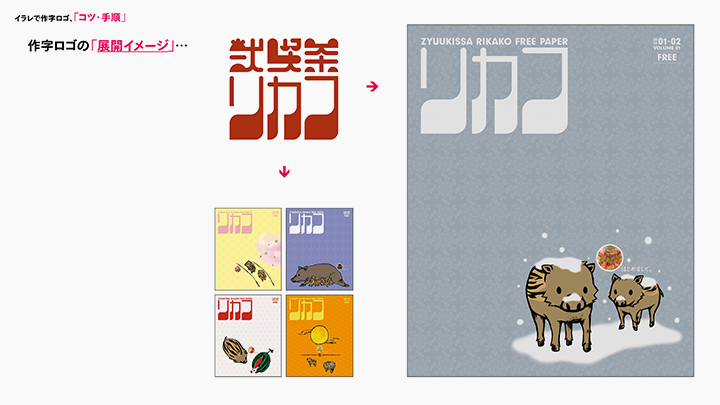
丁寧に調整した、クオリティの高い作字ロゴは、様々な媒体(名刺・DM等)で展開できるデザインとなります。
事例02:「Photo Studio LyLy」
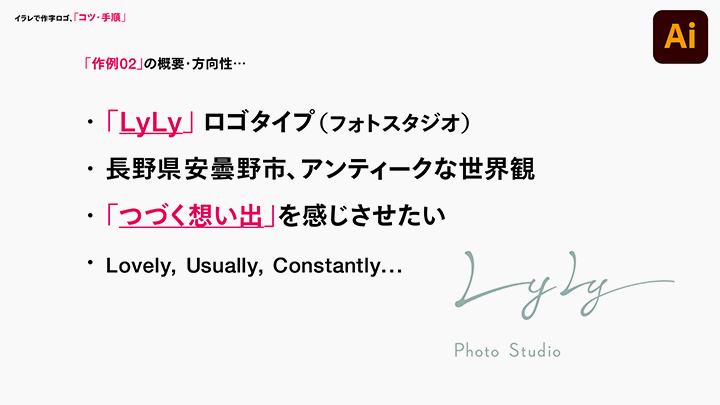
長野県安曇野市にある写真スタジオ、「Photo Studio LyLy」の作字ロゴです。アンティークな世界観と、「想い出の価値」を感じさせるデザインです。
「事例02:Photo Studio LyLy」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。
「Photo Studio LyLy」、Illustratorでの“制作ポイント”
- パスの「なめらかな曲線表現」が、とても重要
- 「アンカーポイント」は、「頂点の手前か少し過ぎた」部分に打つ
- 最初は「直線」で骨格を作り、後から「曲線」を調整
- 「アンカーポイントツール」にて、自然な流れを作る
- 「パスの点」を増減させて、最適な曲線を検証する
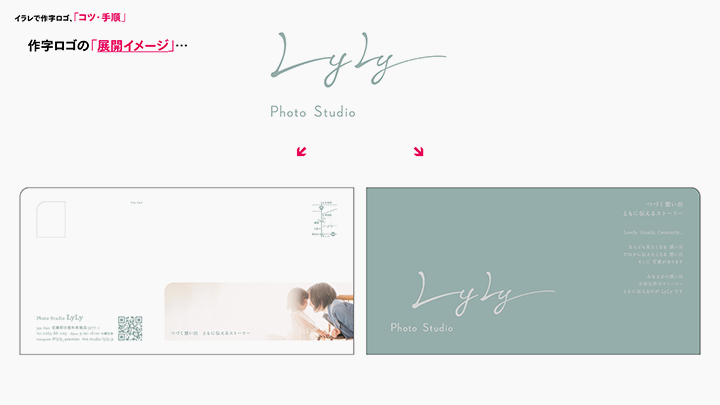
事例03:「イベント『高める』」
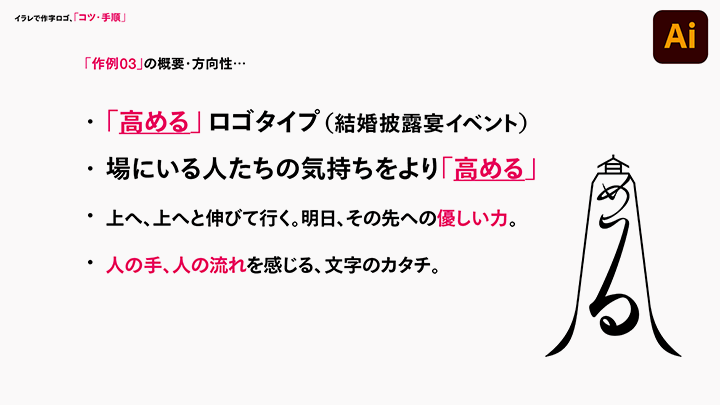
上昇感と伸びる印象を表現した、「イベント『高める』」の作字ロゴです。
「事例03:イベント『高める』」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。
「イベント『高める』」、Illustratorでの“制作ポイント”
- 「直線部分:高」は、「パスの太さ」にて表現する
- 「ナイフツール」にて直線カットをして、シャープなエッジを作る
- 「曲線部分:める」は別途作成して、「直線部分:高」と自然に繋がるよう調整
- 「シンメトリー」になる部分は、対象図形をコピー&反転する
- 「パスの2点」を同じ場所の1点に統合するため、「平均」と「連結」を使う
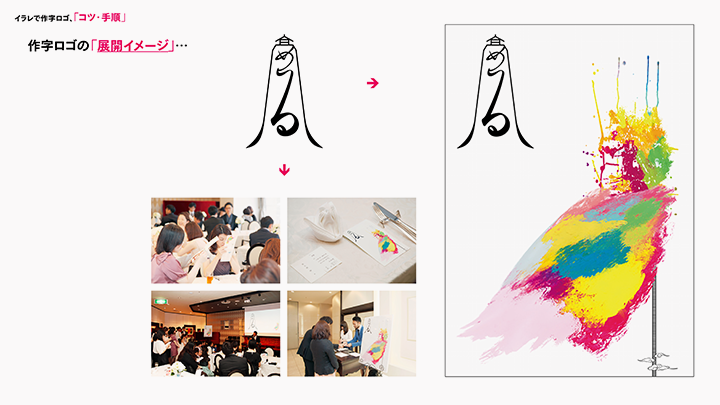
事例04:「渋谷焼肉 KINTAN」
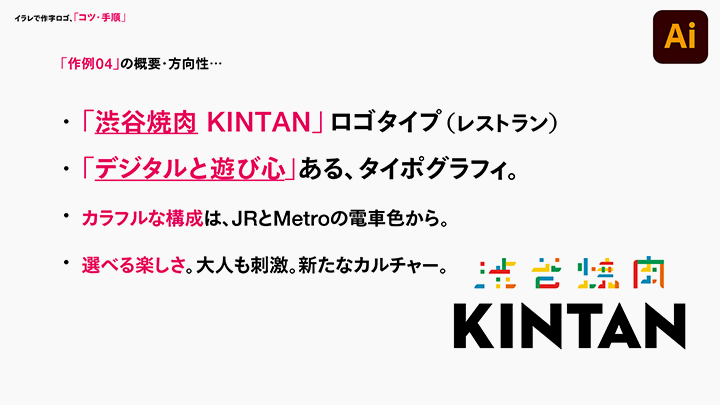
デジタル感と遊び心ある、「渋谷焼肉 KINTAN」の作字ロゴです。
「事例04:渋谷焼肉 KINTAN」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。
「渋谷焼肉 KINTAN」、Illustratorでの“制作ポイント”
- 「正方形」を基本に構成する
- 「ナイフツール」を選び、シフトを押しながら、「45度に図形をカット」
- 「アンカーポイントツール」にて、曲線を調整
- 「複数の色(渋谷駅に関する電車カラー)」を、バランスよく配置
- 「同色部分は統合」して、印刷時の問題を防止する

まとめ
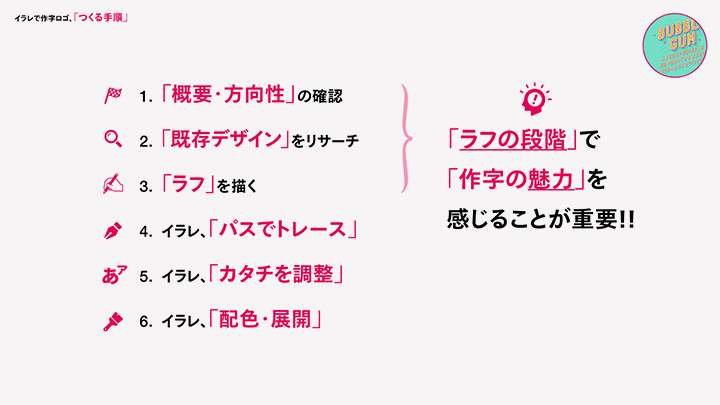
「作字ロゴ」は単なる“文字デザイン”を超えた、「独自の表現力と魅力」を持っています。
「優れた作字ロゴ」を作るためには、「コンセプト設定」「デザインリサーチ」「丁寧なラフ作成」が必須です。
「Illustrator」の機能を活用して、精密に形をつくり、全体のバランスを調整する。
すると、オリジナリティあふれ、クオリティの高い、「作字ロゴ」が完成します。
また、「作字ロゴ」制作方法は様々ですが、大切なのは、「“どの手法”が、“今回のコンセプト”に最適か」を常に考えることです。
「文字の骨格」を理解する。「フォントの特性」を活かす。時には、「直感的な表現」を取り入れる。
これらのテクニックを身につけることで、見る人の心を動かし、記憶に残る、「独自の作字ロゴ」をデザインできるようになります。
ぜひ、実践してみてください!
あなたの“ビジネスにやくだつ”、お知らせ。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。この記事が、あなたの考え方の整理や成長のキッカケになれば、とても嬉しいです。
もし今回の内容が、“いいな”と思っていただけたら、「本記事の拡散」「本ブログのブックマーク」をお願いします!
アトオシのX、Instagramでは、「ビジネスに役立つ、デザイン思考」をデザイン事例と交え、発信しています。こちらのフォローも、よろしくお願いします。
そして、「目的を形にする、ロゴデザインとブランディング」のご依頼やご相談をお考えの方は。アトオシの公式サイトより、お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。
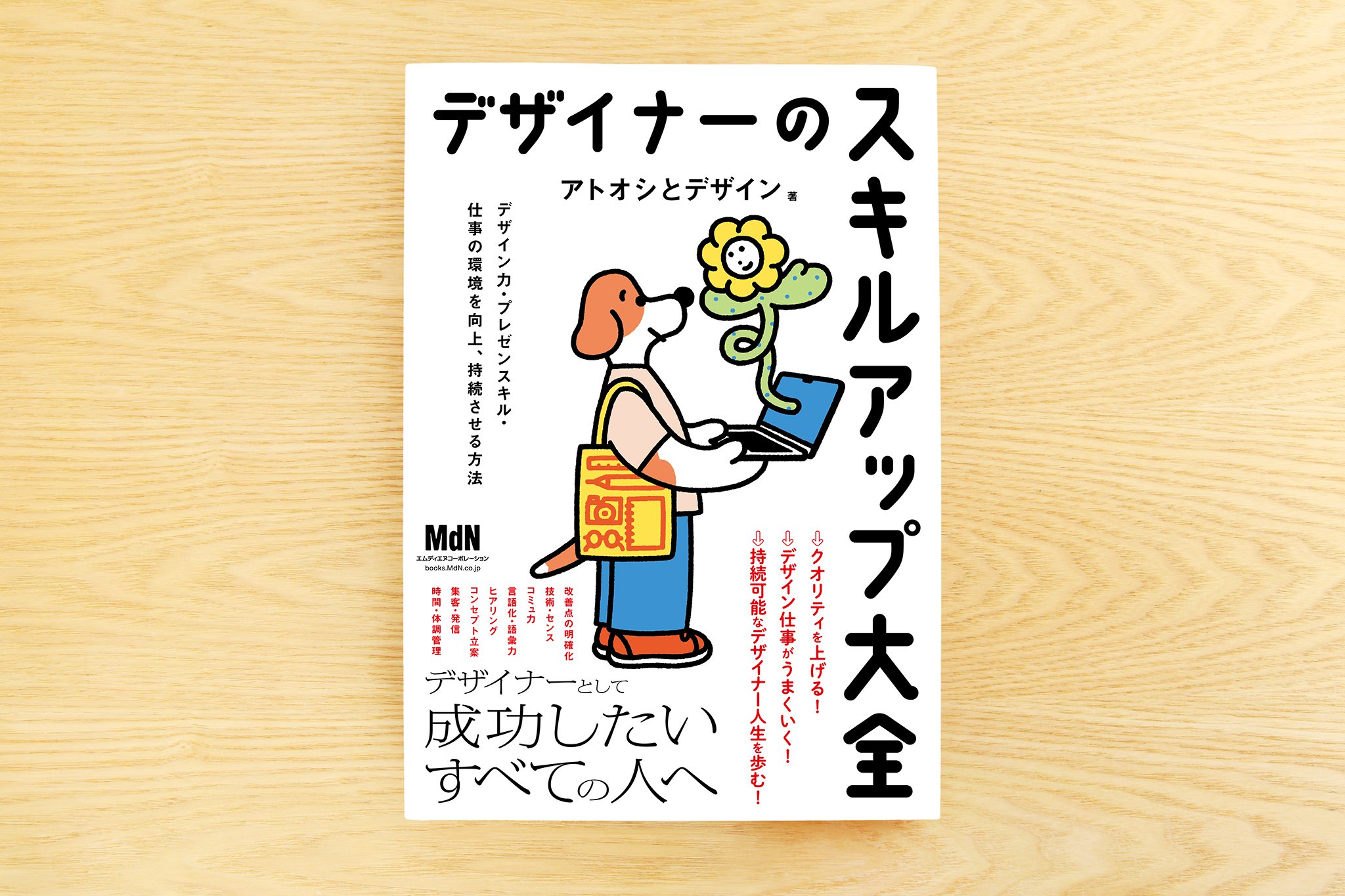
アトオシが書いた著書、『デザイナーのスキルアップ大全』のご購読、各SNSでのご意見やご感想の発信、Amazonレビューも大歓迎です。
この本の目的は、デザイン中級者が持つ、“すべての悩み”を解決し、持続可能な「より幸福度の高いデザイナー人生」を進むための本です。
読むと、“よりよいデザイン成長”ができる、「技術・仕事・時間・体調・人間関係」のつくり方がわかります。